
盆栽を管理する上で、最も頻繁に行い、重要になってくる作業・・・それは、
水やりです。
ほぼ毎日行うからこそ重要な作業になり、水やりを怠ると盆栽は枯れます。
水切れは盆栽を枯らす原因一位と言っても過言ではないでしょう。
盆栽界では「水やり三年」という言葉があります。
毎日修行しているお弟子さんでさえ、ちゃんとした水やりができるまで
3年かかるんですね。
というのも、厳格に管理する場合、盆栽は一本一本水やりの方法を変えます。
鉢の大きさ、根の張り具合、乾き方も個体差があるためです。
ここではポイントだけ上げておきます。
基本は少し乾いてからやる
完全に乾かしてはいけません。
枯れてしまいます。
少し乾いた状態で水をあげる事で根が水を求め、活発に水を吸い上げます。
常に湿っている状態が続くと根腐れしてしまいますので、適度に乾かすことも重要です。
わかりにくい場合、土を触ってみると湿り気があるのか分かりやすいです。
また、苔を貼っていない場合は少し指で土をほじってみて、中が湿っているか目視で確認する事も可能です。
ただ、先述した通り、完全に乾いてしまうと盆栽は枯れてしまうので、水をあげるか判断に迷ったときは水をあげるようにしましょう。

水温は大丈夫?

ホースで水やりを行う場合、夏場などホース内の水が温まっており、蛇口をひねってすぐはお湯が出ることがあります。
このお湯を盆栽にかけてしまうと盆栽にダメージを与えてしまい、枯れる原因になってしまうので、必ず水温を確認し、熱い場合は冷たい水が出るまで待ちましょう。
水は隅々まで、かけ残しがないように
一部かけ残しがあると部分的に枝葉が弱ってしまいます。
鉢の隅々までジョウロの角度を変えながら、しっかり水をあげましょう。


プロも愛用する根岸産業の銅製ジョーロもおすすめです。
初めのうちは水を多めに
水の量は管理しているうち「どの時間に」「どれ位あげれば」「何時頃に」丁度乾いてくるというのが分かってくると思います。
ただ、水を切らせてしまうと最悪枯れてしまうので、最初のうちは鉢の底から水が流れ出る位やっても問題ありません。
余裕ができたら水の量を調整してその盆栽にあった水量を与えてください。
葉水(はみず)を活用する

葉水とは水を葉にかけることです。
植物は葉からも水分を吸収するので、夏場の急速に乾くときや根の状態が悪く、なかなか水の吸い上げが出来ない時なども葉水で補助します。
植物にとって葉水はやさしいものですので積極的に活用していきましょう。
水が入っていかない盆栽にはどぶ漬け!

根が張っていたり、表面の土が固まってしまい水が表面を流れるだけで水が浸透していかない場合があります。
そういう場合は、盆栽よりも一回り以上大きい容器を用意し、鉢が完全に浸かる位まで水を張り、そこに盆栽を漬けます。
これをどぶ漬けと言います。
ブクブクと泡が出てくると思いますので、角度を変えたりして泡が出なくなれば芯まで浸透していますので、取り出します。
しかし、頻繁にどぶ漬けをする必要があるくらい根が張っていたり、土が固まってしまったら植え替えが必要です。
日中水やりが出来ない方へ

置き方の項でも紹介しましたが、朝出る時と帰って来てからたっぷりと水をやって下さい。
もしくはどぶ漬けをして下さい。
置き場所も半日陰に置くようにして下さい。
それだけで水切れの危険性はかなり下げられると思います。
日よけ
朝~昼頃まで日が当たるようにして、その後は日陰になるように調整すると乾きにくくなります。
ただし、片面だけしか日が当たらないと日の当たらない方が弱ってしまうので全体に日が当たるようにしましょう。

どうしても片面しか日が当たらない様でしたら回転台を下に敷いて時々方向を変えてあげると枝葉全体に日光を当てることができます。
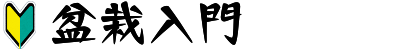

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e6c2e09.4c69b5c4.1e6c2e0a.8c8613dd/?me_id=1239918&item_id=10003641&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivingplaza%2Fcabinet%2Fimg55665707.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cccc4ce.0da8fb15.1cccc4cf.5cceb343/?me_id=1253119&item_id=10002220&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftakisyo%2Fcabinet%2F01211854%2F01305728%2Fimg56476963.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cca827c.fbdb28a4.1cca827d.ea3d751a/?me_id=1366964&item_id=15361357&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyellowshop%2Fcabinet%2Fitem%2F1627%2F21015245626_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
